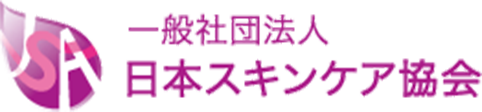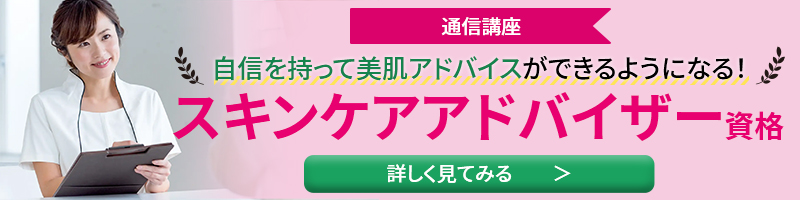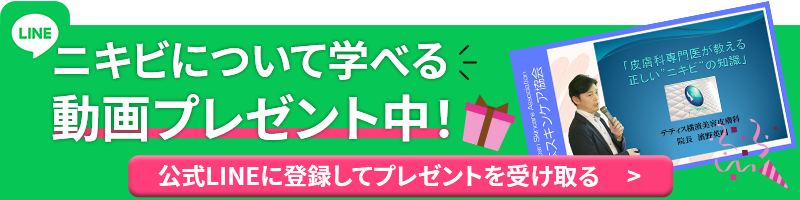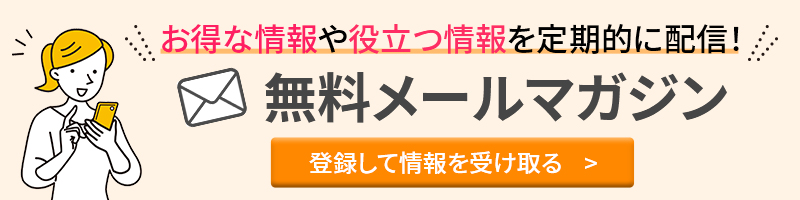2025年11月11日2025年12月18日お肌のトラブルケア,美容と健康のアドバイス
ニキビが治らない?今すぐ見直したいスキンケア習慣

「また同じ場所にニキビができてしまった…」
そんなとき、あなたはどんなケアをしていますか?
一生懸命洗顔して、保湿もしているのに改善しない。
実はそのスキンケア、“やりすぎ”や“足りなさ”が原因になっていることがあります。
本コラムでは、ニキビ肌に悩む女性のために、今日からできるスキンケアの見直しポイントを丁寧にご紹介します。
毎日の小さな習慣を整えることで、肌は必ず変わっていきます。
なぜニキビができるの?原因を正しく理解しよう

「ちゃんと洗顔しているのに、なぜかまた同じ場所にニキビが…」
そんな経験はありませんか?
ニキビは「清潔にしていないからできる」わけではありません。
実は、皮脂分泌・毛穴詰まり・アクネ菌・ホルモンバランス・生活習慣など、複数の要因が重なって発生する“炎症性皮膚トラブル”です。
ここでは、その仕組みとタイプ別の違いを詳しく見ていきましょう。
ニキビの発生メカニズム
私たちの肌には「皮脂腺」があり、そこから分泌される皮脂は、肌を乾燥や外的刺激から守る重要なバリア成分です。
しかし、ホルモンの影響やストレスなどで皮脂分泌が増えると、毛穴が詰まりやすくなります。
毛穴が角栓でふさがると、毛穴の中に常在菌であるアクネ菌が繁殖しやすくなり、炎症を引き起こして赤く腫れたニキビへと進行します。
ニキビの初期段階は、白ニキビや黒ニキビ。
これらはまだ炎症を起こしていない“未炎症性ニキビ”です。
この段階で正しいケアをすれば、跡を残さず改善できます。
思春期ニキビと大人ニキビの違い
ニキビには思春期ニキビと大人ニキビがあり、発生部位や原因が異なります。
思春期ニキビ:Tゾーン(額・鼻)に多く、成長ホルモンの影響による皮脂過剰が主な原因。
大人ニキビ:フェイスライン・あご・口周りなど下半顔に多く、ストレス・乾燥・ホルモン変動・睡眠不足などが原因。
思春期ニキビは「皮脂をコントロールするケア」が中心になりますが、大人ニキビは「保湿・睡眠・ストレス対策・ホルモンバランスの安定」が重要になります。
ホルモンバランスとストレスの影響
女性の肌はエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌バランスに強く影響を受けます。
・排卵期〜黄体期(月経前):プロゲステロンが優位になり、皮脂分泌が増加。
・月経期:ホルモン分泌が低下し、肌が乾燥・敏感に傾く。
このように、月経周期の変化で肌の状態も揺らぎやすくなります。
さらにストレスが加わると、副腎からストレスホルモン(コルチゾール)が分泌され、皮脂腺を刺激します。
結果、Tゾーンやあごにニキビが現れやすくなるのです。
外的刺激によるニキビ
近年では、「マスクによる摩擦」や「メイク残り」が原因で起こる“外的刺激型ニキビ”も増加しています。
マスク内の湿気やこすれは、肌のバリア機能を弱め、炎症を誘発します。
また、落としきれないメイクや皮脂汚れが毛穴に残ると、酸化して黒ずみ・炎症を引き起こします。
「丁寧に落とすケア」を怠ることが、ニキビの第一歩なのです。
あなたのスキンケア、間違っていませんか?

「清潔にしなきゃ!」
「ニキビがあるから、しっかり洗おう!」
――そう思って、一生懸命ケアを続けているのに、なぜか改善しない。
もしかするとその原因は、「やりすぎケア」や「不足ケア」にあるかもしれません。
スキンケアは、正しく行えば肌を整えますが、間違えると逆にバリア機能を壊してしまうこともあります。
ここでは、ニキビを悪化させるNG習慣と、肌質に合った正しいケア方法を丁寧に見直していきましょう。
ニキビを悪化させるNG習慣
ニキビ肌の方に特に多いのが、「落としすぎ」「触りすぎ」「保湿不足」の3つです。
どれも“肌をきれいにしたい”という思いから起こりがちな行動ですが、実は逆効果になっていることがあります。
ゴシゴシ洗顔・長時間洗顔
皮脂や汚れを落とそうと強くこすったり、長時間洗顔したりすると、角質層のうるおいまで奪ってしまいます。
角質層は厚さ0.02mmほどしかない非常に薄い層ですが、外部刺激から肌を守る「天然のバリア」です。
これを壊すと、乾燥や炎症が起こり、結果としてニキビを繰り返す原因になります。
→ 正解は「やさしく・短時間・しっかりすすぐ」。
洗顔料はしっかり泡立て、泡で汚れを包み込むように洗いましょう。
アルコールやメントールの強い化粧水
「スーッとする=肌に効いている」と感じがちですが、刺激の強い成分は皮膚炎や乾燥を招きます。
日本スキンケア協会の公式テキストでも、アルコール・メントール・香料の刺激がバリア機能を低下させることが解説されています。
→ 敏感肌・ニキビ肌の方は、低刺激・無香料タイプを選ぶのが鉄則です。
「脂性肌だから保湿しない」
実はこれも大きな誤解です。
保湿不足で角質が乾燥すると、肌は「乾燥を補おう」として皮脂を過剰に分泌。
その結果、毛穴詰まりや炎症が悪化してしまうのです。
「皮脂を抑えるためにも保湿が必要」という逆転の発想が大切です。
寝不足も、成長ホルモンが分泌されず、肌の修復力が低下するのでしっかりと睡眠はとりましょう。
肌質別の見直しポイント
スキンケアの正解は、「肌質に合わせること」です。
協会のテキストでは、肌質を「普通肌・乾燥肌・脂性肌・混合肌・敏感肌」に分類し、それぞれの特徴に応じたケアを推奨しています。
乾燥肌タイプ
皮脂・水分ともに不足しがちで、外的刺激に弱いタイプ。
セラミド・ヒアルロン酸・アミノ酸などの保湿成分でうるおいをしっかり補給しましょう。
洗顔料はアミノ酸系で、朝はぬるま湯だけでも十分です。
脂性肌タイプ
皮脂分泌が多く、毛穴詰まりを起こしやすいタイプ。
しかし「脱脂しすぎ」は禁物。
水分を補いながら、軽めのジェル状保湿剤でバランスを整えましょう。
皮脂を吸着するパウダー入り乳液や、ビタミンC誘導体入り美容液もおすすめです。
混合肌タイプ
Tゾーンはベタつき、Uゾーンは乾燥。
このタイプには「部分ケア」が有効。
Tゾーンは皮脂コントロール系化粧水、Uゾーンはしっとり保湿アイテムを使い分けましょう。
敏感肌タイプ
バリア機能が低下しやすく、赤みやヒリつきを感じやすいタイプ。
「無香料・無着色・アルコールフリー」の基礎化粧品を選び、摩擦を最小限に。
タオルで顔を拭くときも“押さえるように”が基本です。
朝・夜のスキンケアルーティン例
スキンケアは、「落とす」「与える」「守る」の3ステップで考えるのが基本です。
ここで、ニキビを防ぐための理想的な1日の流れを紹介します。
朝のケア
ぬるま湯で軽く洗顔(皮脂の酸化物だけを落とす)
化粧水で水分補給(手で押さえ込むように浸透)
軽めの乳液またはジェルでうるおいキープ
UVケア(日焼け止めはノンコメドジェニックタイプ)
朝の保湿と紫外線対策は、ニキビ跡の色素沈着を防ぐためにも重要です。
夜のケア
クレンジングでメイク・皮脂を落とす(擦らず30秒以内)
洗顔フォームで泡洗顔(Tゾーン→Uゾーンの順)
化粧水→美容液→乳液(順に重ねてうるおいを閉じ込める)
週1〜2回、酵素洗顔や泥パックで角質ケア
夜のケアでは、「落とす時間」よりも「与える時間」を大切に。
化粧水はコットンでパッティングするより、手のひらで包み込む方が刺激が少なくおすすめです。
正しいスキンケアの基本3原則
落としすぎない(バリア機能を守る)
与えすぎない(毛穴詰まりを防ぐ)
守るケアを怠らない(紫外線・乾燥対策)
この3つのバランスが取れて初めて、肌は健康な状態を維持できます。
スキンケアとは「足すこと」よりも、「整えること」。
つまり、“肌の自然な働きを邪魔しない”ことこそ最良のケアなのです。
ニキビ肌におすすめの正しいスキンケアステップ

「毎日お手入れしているのに、なぜかニキビが治らない」
――その理由は、スキンケアの“手順”や“選び方”の間違いにあることが少なくありません。
肌は生きている器官です。
正しい順序でケアすることで、バリア機能や水分保持力を高め、本来の「治る力」を取り戻します。
ここでは、ニキビ肌の方が今日から実践できる“正しいスキンケアステップ”を、科学的な根拠とともに紹介します。
ステップ① クレンジング ― “落とす”ケアの最初の要
クレンジングは、メイクや皮脂の酸化物を落とし、毛穴の詰まりを防ぐための重要なステップです。
ただし、落としすぎや強すぎる摩擦はバリア機能を壊す原因になります。
★正しいクレンジングのコツ
手と顔の汚れを落としてからスタート(雑菌を防ぐ)
乾いた手でクレンジングを適量とる(大きめのさくらんぼ大が目安)
30秒以内でなじませ、ぬるま湯でやさしくすすぐ
熱すぎるお湯はNG(32〜35℃が理想的)
「クレンジングは短時間で、肌に負担をかけないことが原則」です。
メイクが濃い日でも“こすらず落とす”を意識しましょう。
★おすすめアイテム
- ミルクタイプ:乾燥・敏感肌向け(低刺激)
- ジェルタイプ:脂性肌・混合肌向け(さっぱり感)
- バームタイプ:濃いメイクをしっかり落としたい日用(洗浄力強め)
「メイク残り」はニキビの温床。
どのタイプを使う場合も、肌をこすらず、乳化→すすぎを丁寧に行うことがポイントです
ステップ② 洗顔 ― 清潔と保湿のバランスを保つ
洗顔は、1日の皮脂・ほこり・古い角質を取り除く大切なステップ。
しかし、やりすぎると角質を削ぎ落とし、逆に皮脂が過剰になります。
理想的な洗顔の流れ
手を洗い、雑菌を落とす
↓
洗顔料をしっかり泡立てる(もこもこの泡が理想)
↓
泡で顔を包み込むように洗う(指が肌に触れないように)
↓
ぬるま湯で20〜30回すすぐ
↓
清潔なタオルでやさしく押さえて水分を拭き取る
特に「泡で洗う」ことは重要です。
摩擦によるダメージは、ニキビ跡や色素沈着の原因にもなります。
また、洗顔は1日2回が基本。
朝は「皮脂の酸化物を落とす程度」で十分です。
★洗顔料選びのポイント
- アミノ酸系:低刺激で保湿力を保つ(例:ココイルグルタミン酸Na)
- 弱酸性タイプ:肌のpH(4.5〜6.0)に近く、常在菌を守る
- 無香料・無着色:ニキビ肌への刺激を軽減
ステップ③ 化粧水 ― 水分を「届ける」ケア
洗顔後は、角質が一時的に柔らかくなり、水分を吸収しやすい状態です。
ここで化粧水を与えることで、うるおいの土台を作ることができます。
正しい使い方
洗顔後すぐ、タオルドライしたら10秒以内に化粧水をつける。
手のひらで包み込むように、やさしく押さえる。
コットンを使う場合は摩擦を避け、軽くパッティング。
★成分選びのポイント
- セラミド:バリア機能を補う
- ヒアルロン酸:保水力を高める
- グリチルリチン酸2K:炎症を鎮める
- ビタミンC誘導体:皮脂抑制・毛穴引き締め
日本スキンケア協会の公式テキストでも、化粧水は肌質に合わせて成分を選ぶことが大切とされています。
乾燥肌ならしっとりタイプ、脂性肌ならさっぱりタイプを選びましょう。
ステップ④ 美容液・乳液 ― 水分を「閉じ込める」
化粧水で与えた水分を逃さないように、乳液や美容液でフタをします。
油分が苦手な方でも、ノンコメドジェニック処方(ニキビになりにくい処方)を選べば安心です。
使用のコツ
美容液は肌悩み別に選ぶ。(例:ビタミンC誘導体・ナイアシンアミド)
乳液は1円玉程度の量で十分。Tゾーンは少なめに、Uゾーンはしっかりと。
「重ねすぎ」は毛穴詰まりの原因。軽やかなテクスチャーを選びましょう。
★美容成分例
- ナイアシンアミド:皮脂コントロール・抗炎症
- アゼライン酸:角質正常化
- レチノール誘導体:ターンオーバー促進(ただし刺激があるため夜のみ使用)
ステップ⑤ 日中の「守る」ケア ― 紫外線対策はニキビ予防の一部
紫外線は皮脂を酸化させ、毛穴詰まり・炎症・色素沈着(ニキビ跡)の原因になります。
そのため、日焼け止めもスキンケアの一部として考えましょう。
ポイント
SPF30・PA+++程度で十分。(強すぎるものは刺激に)
ノンコメドジェニック・ミネラルUV処方を選ぶ。
室内でも紫外線A波(UVA)は届くため“毎日使用”が基本。
夕方に皮脂が浮いた場合は、ティッシュで軽く押さえ、日焼け止めを軽く塗り直すのが理想です。
週1〜2回のスペシャルケア
角質の厚みや皮脂の酸化を防ぐためには、定期的なケアも有効です。
- 酵素洗顔:タンパク汚れを分解し、角栓予防に。
- 泥パック:皮脂吸着作用で毛穴を清潔に。
- シートマスク:保湿集中ケアとして夜に使用。
ただし、やりすぎは禁物。
週1〜2回を目安に、「肌が疲れているとき」に取り入れるのがベストです。
季節・環境に合わせたスキンケアの調整
肌は季節や環境で大きく変化します。
春は花粉、夏は皮脂、秋冬は乾燥――それぞれの時期に合わせてアイテムを見直すことが大切です。
★春:
- 花粉・PM2.5対策。
- 帰宅後すぐに洗顔を。
★夏:
- 汗・皮脂が増える季節。
- 皮脂分泌が増えるため、ジェルタイプ保湿剤で軽やかに。
★秋・冬:
- 乾燥でバリア機能低下。
- セラミド配合クリームをプラス。
★花粉・PM2.5シーズン:
- 帰宅後すぐ洗顔で刺激物を落とす。
肌を“季節の変化に合わせて守ること”が、ニキビを防ぐ最大の予防策になります。
生活習慣・食事からニキビを防ぐ

~内側から肌を整える「生活リズムケア」~
スキンケアをどれだけ頑張っても、ニキビが繰り返す――
その原因は、生活リズムや食習慣の乱れにあるかもしれません。
肌は「内臓の鏡」といわれるほど、体の内側の状態が表れやすい場所です。
特にホルモンバランス・腸内環境・睡眠・ストレスの影響は大きく、これらを整えることが本当の“根本ケア”になります。
ここでは、毎日の習慣を少し変えるだけで肌を改善できる、「生活習慣×栄養×心」の3方向からアプローチしていきましょう。
食生活の見直し ― 「肌をつくる」食べ方を意識する
私たちの肌は、日々の食事から得る栄養素によって作られています。
乱れた食生活は、皮脂分泌やホルモンバランスを崩し、ニキビの引き金になります。
まずは、「肌を整える栄養」と「避けたい食べ物」を知ることから始めましょう。
ニキビ改善に役立つ栄養素
| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |
| ビタミンB群 | 皮脂の分泌をコントロール、代謝を促進 | レバー、納豆、卵、マグロ、豚肉 |
| ビタミンC | 抗酸化・炎症抑制・コラーゲン生成 | ブロッコリー、キウイ、柑橘類 |
| ビタミンE | 血行促進・抗酸化 | アーモンド、かぼちゃ、アボカド |
| 亜鉛 | 皮膚の再生・傷の修復 | 牡蠣、ナッツ、赤身肉 |
| 食物繊維 | 腸内環境を整える | ごぼう、海藻、オートミール |
| 発酵食品 | 善玉菌を増やす | 納豆、ヨーグルト、味噌、キムチ |
特に「腸内環境」と「皮膚状態」には密接な関係があり、腸が乱れると老廃物が排出されにくくなり、ニキビの原因物質が血液を通じて全身に巡ります。
腸を整えること=肌を整えることなのです。
控えたい食品
- 揚げ物・スナック菓子(酸化した油は皮脂を増やす)
- 白砂糖・清涼飲料水(血糖値の急上昇で皮脂分泌促進)
- ファストフード(トランス脂肪酸は炎症を悪化)
- カフェイン・アルコールの摂りすぎ(ホルモンバランスを乱す)
完璧に避ける必要はありませんが、“毎日”ではなく“ときどき”にする意識が大切です。
睡眠の質を上げて「肌の修復力」を高める
睡眠中、肌はもっとも活発に再生・修復を行っています。
特に午後10時~午前2時は「肌のゴールデンタイム」と呼ばれ、成長ホルモンが多く分泌される時間帯。
この時間にしっかり眠ることで、ターンオーバーが整い、炎症が鎮まりやすくなります。
良質な睡眠のための3つのポイント
- 就寝1時間前にはスマホ・PCをやめる
ブルーライトは脳を覚醒させ、眠りを浅くします。
- 照明を落として副交感神経を優位に
暖色系の照明やアロマ(ラベンダー、オレンジ)でリラックス。
- 寝る直前の食事・カフェインを控える
消化にエネルギーを使うと、肌修復が後回しになります。
- 理想は、6〜7時間以上の深い睡眠。
「長さ」よりも「質」を意識して、眠りの環境を整えましょう。
ストレスとの付き合い方 ― ホルモンバランスを守る心のケア
ストレスは、ニキビ悪化の大きな原因のひとつです。
ストレスを感じると、副腎からストレスホルモン「コルチゾール」が分泌され、皮脂腺を刺激して皮脂を過剰にします。
また、自律神経が乱れることでターンオーバーが滞り、毛穴詰まりを起こしやすくなります。
今日からできるストレス対策
深呼吸をする(3秒吸って6秒吐く呼吸法)
1日15分の散歩やストレッチ(血流と代謝を促進)
香りを活かすアロマ入浴(ラベンダー・ゼラニウム・ベルガモットなど)
「頑張りすぎない日」をつくる(心も肌も休ませる)
日本スキンケア協会のカウンセラーテキストでも、「肌トラブルの背景には心のストレスがある」と述べられています。
スキンケアだけでなく、“自分をいたわる時間”を持つことも、肌改善の重要なプロセスなのです。
運動と血流ケア ― 肌代謝を高める
適度な運動は、血液循環を促し、老廃物の排出を助けます。
血流が滞ると、酸素と栄養が肌細胞に届きにくくなり、くすみや炎症を悪化させる原因に。
1日20〜30分のウォーキング、ストレッチ、ヨガなど、軽く汗ばむ程度の運動を習慣にしましょう。
また、フェイシャルマッサージやリンパケアも有効です。
協会監修のフェイシャリスト資格テキストでも紹介されているように、「血流を整えることは肌トラブルの予防につながる」とされています。
「肌改善週間」をつくる ― 継続できる習慣化のコツ
生活リズムを一度に変えるのは難しいもの。
そこでおすすめなのが、“1週間単位の肌改善スケジュール”です。
| 曜日 | 取り入れる習慣 |
| 月曜 | 洗顔方法を見直す(泡の質・時間を意識) |
| 火曜 | 野菜中心の食事を意識 |
| 水曜 | 夜の保湿パックを追加 |
| 木曜 | スマホを早めにオフ・アロマで入浴 |
| 金曜 | 軽い運動で血流を促す |
| 土曜 | 早寝して肌のゴールデンタイムを確保 |
| 日曜 | 鏡で肌チェック&スキンケアの見直し |
「完璧にやろう」と思わず、“できることから一つずつ”を積み重ねることが、続けられる秘訣です。
肌は約28日で生まれ変わります。
1ヶ月後には、きっと手触りの違いを感じるはずです。
それでも治らないときは?専門家に相談を

~自己流ケアから一歩進んで、“プロの視点”で肌を見つめ直す~
どんなに丁寧に洗顔し、保湿をしても、なかなか改善しない。
同じ場所に繰り返しできる。
痛みや赤みが強く、気持ちまで落ち込んでしまう――。
そんなときこそ、「自分の努力が足りない」と責めないでください。
ニキビは体の内側・外側・心のバランスが複雑に関わる皮膚疾患。
セルフケアで改善しない場合は、専門家のサポートが必要な段階に来ているサインです。
ここでは、皮膚科とスキンケア専門家の両方からのアプローチを紹介します。
皮膚科での治療 ― 医学的視点で“原因”を見極める
皮膚科での診察を受ける最大のメリットは、「原因の特定」と「適切な治療」ができること。
ニキビには、ホルモン性、炎症性、薬剤性などさまざまなタイプがあり、医師はそれを見分けた上で治療方針を立てます。
主な皮膚科治療
- 抗炎症外用薬
ダラシンTゲル、アクアチムクリームなど
炎症や赤みを抑え、悪化を防ぐ。
- 角質剥離・毛穴詰まり改善薬
ディフェリンゲル(アダパレン)や過酸化ベンゾイル(ベピオゲル)
角質の厚みを整え、毛穴詰まりを防止。
- 内服治療
ビタミンB群、C、Eの補給
女性の場合はホルモン治療(低用量ピルなど)で周期性ニキビを改善。
- 美容医療的治療
ケミカルピーリング(酸による角質除去)
光治療・レーザー(炎症や色素沈着の改善)
これらの治療は、皮膚のターンオーバーを正常化させることが目的です。
「薬で治す」というより、肌本来の修復力を助けるという考え方が基本にあります。
医師に伝えると良い情報
- いつ頃から繰り返しているか
- 特にできやすい部位(あご・頬・背中など)
- 使用している化粧品やサプリメント
- 生活リズム・ストレス状況
こうした情報を共有することで、医師はより正確に原因を判断できます。
「皮膚科=最後の手段」ではなく、肌を科学的に理解するパートナーと考えて受診しましょう。
サロン・カウンセラーに相談する ― 「生活」「心」「習慣」から整える
皮膚科が「治療」を担当するのに対し、サロンやカウンセラーは「生活・スキンケア習慣・心理サポート」を行う場所です。
特に大人ニキビの場合、ストレスや生活リズムの乱れが関係するため、カウンセリングによるアプローチが非常に有効です。
スキンケアカウンセラーとは
「スキンケアカウンセラー」とは、単に化粧品やお手入れ方法をアドバイスする人ではありません。
皮膚科学・化粧品科学・心理学の知識を総合的に学び、肌と心の両面から人を支える“美容の専門家”です。
日本スキンケア協会の認定資格制度では、医師・大学教授・研究者が監修し、皮膚の構造やターンオーバー、ホルモンバランス、生活習慣の関係性まで体系的に学びます。
また、カウンセリング心理学やストレス理論も学習し、「肌トラブルの背景にある心の状態」にまで寄り添うことができるように設計されています。
たとえば、同じ「ニキビ」に悩むお客様でも、原因は人によって異なります。
ある人はホルモン変動が影響し、ある人はストレスや睡眠不足、またはスキンケアの摩擦が原因かもしれません。
カウンセラーは、肌の状態・生活習慣・心理状態の三方向から丁寧にヒアリングを行い、「その人に合った最適なケアプラン」を提案します。
相談する価値は「寄り添い」と「客観性」
スキンケアカウンセラーが最も大切にしているのは、“寄り添う姿勢”と“正確な見立て”です。
お客様自身が「肌を責めてしまう」「どうしても自己流になってしまう」――
そんなときに、第三者の専門家として冷静かつ客観的に現状を整理し、無理のない改善策を一緒に考えます。
また、医療と異なり、生活全般を見直すことができるのもカウンセラーの強みです。
食事・睡眠・ストレス・スキンケア製品の使い方など、“日常の中の小さなズレ”を見つけて整えるサポートができます。
そのため、皮膚科治療と併用する方も多く、医療・美容・心理の“橋渡し役”として信頼を得ています。
カウンセリングは「肌を通して心を整える時間」
カウンセリングでは、単に肌の表面を観察するだけでなく、「なぜそのケアを選んだのか」「どんなときに肌が荒れるのか」といった質問を通じて、お客様の“生活リズム”や“心の癖”まで丁寧に読み取ります。
それはまるで、肌の声を代弁するような作業です。
会話の中で気づきを促し、「自分の肌とどう向き合えばいいか」を一緒に考える――
それがスキンケアカウンセラーの役割です。
彼らは、肌の専門家であると同時に、心の伴走者。
“肌を整えることは、自分を大切にすること”という理念のもと、お客様が自信を取り戻す瞬間を支えています。
まとめ:スキンケアを見直せば、肌は必ず変わる
ニキビケアのゴールは「一晩で治すこと」ではなく、肌が本来持つ力を取り戻すことです。
正しい洗顔・保湿・紫外線対策・生活習慣。この4つを続ければ、肌は必ず応えてくれます。
ニキビは“肌からのサイン”。
焦らず、自分の肌に優しく向き合うことが一番の近道です。
そして、困ったときは信頼できる専門家に相談を。
あなたの肌は、今からでも生まれ変われます。
▶関連記事:吹き出物やニキビはなぜできる?効果的な改善法や予防法を紹介