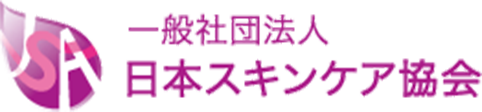美容コラム
-
みずみずしいうるおいのある素肌6 表皮基底細胞と表皮基底膜との接着
2023.1.18
表皮は、真皮側から基底層、有棘層、顆粒層、角層の4層構造からなり、 その大部分は表皮角化細胞によって構成されています。 隣接した表皮角化細胞間にはデスモソーム(desmosome)や 密着結合(tight junction)など、複数の細胞間接着構造が存在し、これらの構造によって表皮角化細胞が互いに接着しています。 デスモソームは、デスモプラキン(desmoplakin)な…
-
ボトックス注射は良い?悪い?≪後編≫
2023.1.17
前回に引き続き今回も「ボトックス注射は良い?悪い?」についてご紹介します。 ボトックス注射で使用する製剤の主成分は、ボツリヌス菌から採取したタンパクです。 菌そのものではありません。 このタンパクは神経伝達物質の放出を阻害し、目的とする筋肉のみ、収縮を抑制するため、表情に伴うしわがよりにくくなります。 ボツリヌス菌というと細菌兵器や食…
-
みずみずしいうるおいのある素肌-5 表皮細胞間の接着とバリア機能
2022.12.20
表皮角化細胞は基底細胞層で分裂し、有棘細胞,顆粒細胞と分化しながら最終的に角質細胞(角層)へと角化します。 角層は空気と生体との境目に形成されるので、胎児や水中で生息している生物にはありません。 このように、生体の最外層が空気とのバリア構造を保つために外的環境に敏感に対応して、角化が行われ、角層が形成されるのです。 &n…
-
みずみずしいうるおいのある素肌-4 モイスト&エモリエント バランス
2022.12.13
健やかで美しい肌をつくり、保つためには「モイスト&エモリエント バランス」が重要です。 モイスト&エモリエント バランスとは、肌の不足した水分・油分を、スキンケア(化粧水・乳液)に含まれる水分・保湿剤・油分でバランス良く補うことで肌を整えることです。 化粧品に配合されているモイスト成分である水性保湿成分(グリセリン、BG、ソルビトールなどのポリオ…
-
しみと美白
2022.11.28
皆さんは「しみ」と言うとどういうものを考えますか? 「しみ」という言葉は使い勝手が良く、頻繁に聞かれる言葉です。 しかし「しみ」そのものを理解し、お客様へ情報としてどのように提供するかでお客様からの信頼度や対処方法が異なります。 しみは主に褐色の色素斑とされていますが、 最も解りやすく言うと茶色、褐色、黒色、青色など色のついた斑状のものと解釈できます。 色…
-
高い保湿力のある植物多糖体「シロキクラゲ多糖体」
2022.11.9
シロキクラゲ多糖体(Tremella Fuciformis Polysaccharide)は、シロキクラゲ科のシロキクラゲ(学名:Tremella fuciformis、英名:Snow fungus)から得られる多糖体です。 グルクロン酸を約20%含有する酸性へテロ多糖体、マンノースを主鎖にキシロースとグルクロン酸を側鎖に持ちます (図1)。 シ…
-
ビタミンCのあれこれ⑦
2022.10.12
関連記事:ビタミンCのあれこれ①に関する記事はコチラ 関連記事:ビタミンCのあれこれ②に関する記事はコチラ 関連記事:ビタミンCのあれこれ③に関する記事はコチラ 関連記事:ビタミンCのあれこれ④に関する記事はコチラ 関連記事:ビタミンCのあれこれ⑤に関する記事はコチラ 関連記事:ビタミンCのあれこれ⑥に関する記事はコチラ ビタミンCは、体内で…
-
抗菌美肌効果のある「バンウコン根エキス」
2022.9.12
サンナ(バンコウ)の特徴・効果 サンナ(山奈、学名: Kaempferia galanga、和名:バンウコン)はショウガ科(Zingiberaceae)バンウコン属多年生草木の匍匐性の植物で、南インドが原産国の植物で、広東、広西、福建、台湾などの地域に分布します。 現在は東南アジアや中国南部でも栽培されています。 高さは10cmほどしか伸びませ…
-
注目の美容成分 老化防止・抗炎症作用・保湿作用のある「ウチワサボテンエキス」
2022.8.8
メキシコで栽培されたOpuntia streptacantha の茎のエキスです。 サボテンはメキシコでは重要な植物であり、栽培されたOpuntia属を除く全ての種がワシントン条約の規制対象となっているが、本品は栽培されたOpuntia属にあたるためワシントン条約の規制対象外です。 化粧品の表示名称は、オプンティアストレプタカンサエキス、INCI名はOpuntia Strept…
-
抗炎症作用のある「ビワ葉エキス」
2022.7.15
枇杷(学名:Eriobotrya japonica 英名:Loquat)はバラ科の植物で、日本の暖地に自生しまたは栽培される常緑喬木です。 枇杷は、中国を原産とし日本には9世紀(801-900年)前後に渡来したと推定されており、江戸時代の幕末(1853-1869年)に清国から大果種が長崎に伝えられたことをきっかけに日本各地に普及しています。 枇杷…